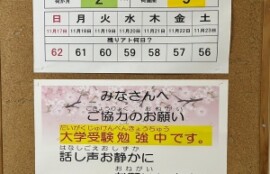無料相談または無料体験授業 ご予約はこちら
偏差値より「答案用紙」が成績を伸ばす|高1・高2必見
「模試の点数が思ったより低かった」
「記述式は部分点の基準が分からない」
「何をどう復習すればいいのか分からない」
そんな悩みを抱える高校1・2年生に伝えたいのが、
模試は“受けた後”が本番ということです。
特に記述模試では、点数や偏差値よりも“自分の答案用紙の中身”にこそ、伸びるヒントが詰まっています。
◆ なぜ「記述模試の解き直し」が重要なのか?
記述模試の特徴は、選択問題と違い「書き方」や「論理の構成」まで評価されること。
点数だけを見ても、自分がどこで減点されたかは分かりません。
例えば──
-
英語の自由英作文:「主張は良いが構文ミスで減点」
-
国語の現代文記述:「主語や述語が曖昧で採点者に伝わらない」
-
数学の証明問題:「解法は合っているが、必要な前提が抜けていて0点」
つまり、模試の得点=学力ではなく、答案表現力×採点基準の理解度です。
だからこそ、「模試の解き直し」は点数アップに直結する最強の学習なのです。
◆ 【保存版】記述模試の正しい解き直し方法
記述式模試の復習・解き直しを効果的に行うために、以下の5ステップを踏みましょう。
① 自力で“再現答案”を書いてみる
まず、模範解答を見ずにもう一度解き直してみることで、「どこまで自力でできたか」が見えます。
-
解けると思っていたが実は曖昧だった
-
書き出しでつまずいていた
-
字数制限に収まらない書き方をしていた
👉 自分の「解答プロセスの弱点」が分かります。
② 模範解答との違いを分析する
模範解答は“正解例”というより**“高得点になる解答の型”**。
違いを見るべきは、内容そのものよりも【構成・表現・論理】です。
-
なぜその接続詞を使っているのか?
-
どの部分に根拠を置いているのか?
-
何文字でどこまで情報を詰めているのか?
👉 再現性の高い「答案構造」を吸収しましょう。
③ 採点者の立場で自分の答案をチェック
模試の採点は「読んで納得できるか」が大前提。
自分の答案を採点者の視点で読み直してみると、見え方が変わります。
-
読み手に伝わるか?
-
抜け落ちている前提条件はないか?
-
言い換えのレベルは適切か?
👉 「通じる答案」を意識することで表現力が伸びます。
④ 「得点を逃した原因」を記録に残す
原因分析をしないと、次の模試でまた同じミスをします。
たとえば以下のように簡単な記録を残しましょう。
| 問題 | ミスの内容 | 原因 | 改善策 |
|---|---|---|---|
| 国語 大問2 | 0点 | 根拠が曖昧 | 具体例で補強する |
| 数学 大問3 | 部分点のみ | 証明のゴールが曖昧 | 論理の結論を先に示す |
👉 「模試復習ノート」や「記述フィードバックシート」を活用すると効果的です。
⑤ 次に同じ形式が出たらどう書くかを明文化
ここが一番重要です。
解説を理解して満足するのではなく、「自分の解答パターン」にまで落とし込むことが成績向上の鍵。
例:
・英作文→主張→理由→例→結論 の型で80〜100語にまとめる
・国語記述→主語と述語の対応に注意/二文構成で整理する
・数学証明→「使う条件」「導きたいこと」を先に明示する
◆ 現論会なら、記述答案の“見え方”が変わる
現論会では、模試後に以下のようなサポートを授業で行っています。
-
✔ 生徒自身が採点者の視点になって解答を分析
-
✔ 点数だけで終わらせない「模試フィードバック」
-
✔ 解き直し結果を次の課題設定に活かす「模試→計画変換指導」
受験は、“振り返る力”のある人が最後に伸びます。
◆ 最後に|記述模試は「答案の成長記録」
模試は偏差値を測るものではありません。
「自分がどう書いたかを可視化し、次にどう伸ばすかを考える」ための教材です。
高校1・2年のうちから、
-
ただの“点数確認”で終わらないこと
-
解き直しの“質”にこだわること
-
自分の“答案を分析する視点”を持つこと
この3つを習慣化できた生徒が、受験学年で一気に飛躍します。