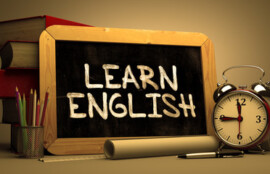無料相談または無料体験授業 ご予約はこちら
0. そもそも指数・対数とは?
指数とは
指数は 「同じ数の掛け算を何回したかを表す道具」 です。
23=2×2×2=8
「2を3回かけると8になる」という意味ですね。
この考え方を広げると、ゼロ回(ゼロ乗)、逆数(マイナス乗)、ルート(分数の指数)も自然に定義できます。
対数とは
対数は 指数を逆に考える道具 です。
ac=b⟺ c=logab
「a を何回かけたら b になるの?」という質問に答えるのが対数。
-
指数は「答えを求める」
-
対数は「何乗すればいいかを求める」
という役割分担です。
1. 公式一覧
指数の公式まとめ
| 法則 | 数式 | 直感的な意味 |
|---|---|---|
| 積の法則 | am⋅an=am+n | 掛け算したら回数を足せばいい |
| 商の法則 | am÷an=am−n | 割り算したら回数を引けばいい |
| べき乗の法則 | (am)n=amn | 「回数をさらに繰り返す」と掛け算になる |
| 積の展開 | (ab)n=anbn | まとめて掛けてもバラして掛けても同じ |
対数の公式まとめ
| 性質 | 数式 | 直感的な意味 |
|---|---|---|
| 積の公式 | loga(MN)=logaM+logaN | 掛け算は足し算に変わる |
| 商の公式 | loga (M/N)=logaM−logaN | 割り算は引き算に変わる |
| べきの公式 | loga(Mr)=rlogaM | 指数は前に持ってこれる |
| 底の変換公式 | logaM=logbM/logba | 別の底に変換できる |
2. 指数の公式はなぜ成り立つのか?
(1) 積の法則
am⋅an=am+n
「2を3回かける」と「2を2回かける」を合わせれば、結局「2を5回かける」ことになります。
例: 23⋅22=(2×2×2)⋅(2×2)=25
だから指数は足し算になります。
(2) 商の法則
am÷an=am−n
「2を5回かけたもの」を「2を2回かけたもので割る」と、「残りの3回分」が生き残ります。
例:
25÷22=(2×2×2×2×2)/(2×2)=23
これが「指数を引き算する」理由。m<n のとき逆数が出てくるので、負の指数=逆数 となります。
(3) べき乗の法則
(am)n=amn
「2を3回かけたもの」をさらに4回かけるとどうなるか?
(23)4=(23)×(23)×(23)×(23) = (2×2×2) ×(2×2×2) ×(2×2×2) ×(2×2×2) =212
つまり「3を4回足す」ことになり、掛け算 3×4 が出てきます。
(4) 積の展開
(ab)n=anbn
「ab を3回かける」と考えると:
(ab)(ab)(ab)=(a⋅a⋅a)(b⋅b⋅b)=a3b3
「まとめて掛けても、バラして掛けても同じ」だから成り立つのです。
3. 対数の公式はなぜ成り立つのか?
(1) 積の公式
loga(MN)=logaM+logaN
logaM=p, logaN=q とすると対数の定義より
M=ap,N=aq
掛け算すると
MN=ap⋅aq=ap+q
だから
loga(MN)=loga(ap+q)
となります。
(2) 商の公式
loga (M/N)=logaM−logaN
同じく
M/N=ap-q
となり、対数を取ると引き算の形が出てきます。
loga(M/N)=loga(ap-q)
(3) べきの公式
loga(Mr)=rlogaM
logaM=p の時 M=ap
この時
Mr=(ap)r=apr
だから
loga(Mr)=loga(apr)=pr=rlogaM
(4) 底の変換公式
logaM=logbM/logba
logaM=p の時 M=ap
両辺の対数を底をbとして取ると
logbM=logb(ap)=plogab
よって
これが底の変換公式です。
無料相談または無料体験授業 ご予約はこちら
4. まとめ
指数・対数の公式は「ただ覚えるもの」ではなく、掛け算や割り算の性質をそのまま保つために必然的に生まれたものです。
-
指数法則 → 掛け算の回数を数えれば納得できる
-
対数の公式 → 指数のルールを逆向きに読めば導ける
つまり、「なぜそうなるか」を理解してしまえば、公式を忘れても自分で再現できます。
指数・対数は“暗記の敵”ではなく、“理解すれば一生ものの武器”になる分野です。